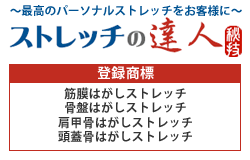昔の常識 → 今では非常識「重心は“かかと寄り”が安定する」

昔の常識 → 今では非常識
「重心は“かかと寄り”が安定する」
ストレッチの達人® 東京の方お困りですか?
✅ よくあった誤解
- 靴の中敷きや姿勢指導で「かかと重心が正解」とされていた
- 立ち仕事やデスクワーク時に「踵に重心を置いて楽に」と指導されていた
- 骨盤が立ち、姿勢が良くなると誤認されていた
❌ 実は「かかと寄り重心」は以下のリスクが…
- 足趾(特に母趾球)が使えない → バランス不安定
→ 地面への“グリップ力”が低下し、転倒リスクが増す - “後ろ重心”が姿勢を崩す
→ 骨盤が後傾し、猫背やストレートネックにつながる - ふくらはぎが緊張しやすく、血流低下・むくみやすい
→ 第二の心臓であるふくらはぎが上手く機能しない - 反り腰・腰痛・首こりの原因にも
→ 骨盤の傾きや肋骨の位置が乱れ、上半身の代償運動が始まる
✅ 今の正解:「母趾球〜足趾で支える“前足部重心”」
- 重心は「足裏3点(踵・小趾球・母趾球)」で支えるのが理想
→ 特に“母趾球”と“足趾”を活用することが安定と動作の鍵 - “前足部重心”が反射機能とバランスを活性化
→ 人間本来の「立ち直り反応(バランス調整)」が使えるようになる - スポーツ選手も“前重心”が基本
→ 走る・跳ぶ・方向転換など、すべて“重心前方”が前提の動作 - 普段の立位でも「足指が地面をつかむ意識」で姿勢が整う
→ 骨盤が自然と立ち、腹圧が入り、姿勢保持が楽に
🔄 具体的な改善ポイント
- 踵体重ではなく「足指・母趾球」で“押す”感覚を意識
- 足趾をしっかり開くトレーニングやセルフストレッチが有効
- 立位時に「足指が浮いてないか」をチェックする
- バランスディスクや足趾ジャンケンなどで足裏機能を高める
💡まとめ
「かかと重心=安定」は過去の話。
現在は「足趾を使える重心設計」こそが、パフォーマンスと姿勢安定の鍵。
スポーツや日常生活の質を高めるためにも、“母趾球重心”を意識した足の使い方を再学習することが重要です。
🎓 監修:山﨑 信治(やまざき しんじ)
中医学博士/ストレッチ専門店「ストレッチの達人®」創始者・代表
🟦 専門家プロフィール
臨床経験22年以上、施術実績45,000件以上筋膜・骨格・経絡を統合した独自施術を開発
開発施術:
- 骨盤はがし - 肩甲骨はがし
- 肋骨リブート - 可動域ブースト
- 体軸チューニング - トリガーリリース
(商標登録済含)
プロアスリート・芸能関係者・高齢者まで幅広く対応
宝塚歌劇団、Jリーグ、五輪代表選手など専属指導歴あり
講演・発表実績:30回以上
全国放送多数「ズームインスーパー」、地方放送多数、女性誌など出演・掲載多数
🟥拠点(全国対応)
福岡|広島|兵庫|大阪|名古屋|東京|札幌(全国あり)
※公式HP:https://stretch-tatsujin.com