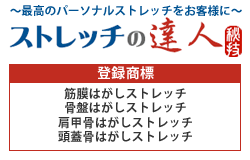【専門家解説】ストレッチの達人が考案!
可動域ブースト・体軸チューニング・肋骨リブートとは?
【専門家解説】ストレッチの達人が考案!
可動域ブースト・体軸チューニング・肋骨リブートとは?
🧠なぜ今、新たなストレッチ技術が必要なのか?
従来のストレッチは「筋肉を伸ばす」ことに特化してきました。
しかし、現代人の体は…
- 長時間のスマホ・PC作業で固まった姿勢
- 浅い呼吸・体幹の弱化・左右差の増大
- “可動域の制限”が筋肉ではなく「神経系」「関節包」「重心の崩れ」にある
といった複雑な要因が絡んでおり、
「ただ伸ばすだけ」では改善できない体が増えています。
✅ストレッチの達人が考案した3つの新技術とは?
● 可動域ブースト
〜今まで動かなかった関節が動き出す〜
- 筋肉・筋膜・関節包・神経系への多角的アプローチ
- 自分の脳が「ここまでしか動かせない」と制限していた動きをリセット
- 特に肩・股関節・膝関節などの可動域改善に効果的
● 体軸チューニング
〜バランスの崩れを整え、動作を安定させる〜
- 体の「軸」「重心」がブレることで出ていた不調を再構築
- 骨盤の歪み・左右差・足裏から頭頂までの重心ラインを調整
- 運動時だけでなく、日常の立ち姿・歩き方・疲れやすさにも直結
● 肋骨(はがし)リブート
〜呼吸の“構造”を目覚めさせ、姿勢の土台を再起動〜
- 肋骨と胸郭まわりの筋膜をリリースし、呼吸の質を高める
- 呼吸に関わる筋肉(横隔膜・腹横筋・肋間筋)を活性化
- 呼吸が深くなることで自律神経・代謝・姿勢制御まで改善
✅まとめ|次世代ストレッチは「動き・軸・呼吸」を整える時代へ
- 従来の“筋肉を伸ばす”を超えたアプローチで体が変わる
- 可動域・軸・呼吸の3方向から根本改善
- スポーツをしていない人にも効果が大きく、日常動作に直結
🎓 監修:山﨑中医学博士/ストレッチの達人代表
臨床経験20年以上。プロアスリートから高齢者まで幅広く指導。
ストレッチの達人®
福岡 広島 兵庫 大阪 名古屋 東京 札幌